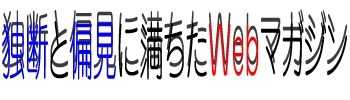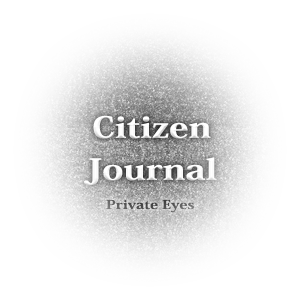東京・八王子市にそびえ立つ【高尾山】が開いている【健康登山】が人気だ。
Twitterユーザーの中でも、健康登山に必須のアイテムとも言える手帳を見せあうツイートが目立っている。
高尾山の健康登山と手帳の人気について迫ってみよう。
高尾山の健康登山とは?
今日は健康登山で高尾山、薬王院21回満行達成どえす! pic.twitter.com/93hWIdLPYZ
— 俺 拝 (@volmetman) 2014年7月12日
高尾山の健康登山は高尾山薬王院が、登山者に向けて平成11年から開始されたものだ。
薬王院側のコンセプトとしては、登山客の健康のお手伝いを担うというものであり、現在は薬王院主催の健康登山の会員数は、5000人を超える勢いを見せている。
高尾山は標高599mと比較的に高くない山であるということと、東京西部の象徴であることから、手軽な登山スポットとして人気が高い。
関東近県の方達は、小学校の遠足などで必ず一度は登山を経験したことはあるだろう。
また、高尾山の健康登山には無くてはならないアイテムがある。
それが健康登山手帳である。
高尾山の健康登山にかかせない手帳
高尾山お決まりの健康登山手帳印も無事いただけました☆ pic.twitter.com/qmsWBP26Up
— るん✯ (@Ru_n08y) 2014年11月21日
薬王院が会員に配る健康登山手帳は正式名称は【高尾山健康登山の証】というものだ。
この手帳は一冊600円であり、登山に来た人間の誰もが購入する事が出来る。
そして、手帳の購入とともに会員としてみなされるようだが、特に個人情報の明記は必要ない。
手帳のサイズは約12cm×約11cmと、持ち運びに便利なサイズであり、高尾山の健康登山をする会員はこの手帳と供に、自分の成長と証を蓄える楽しさを味わっていくことになる。
高尾山・健康登山手帳の使い方など
今日のミッシヨンその1。
高尾山健康登山手帳に、これまでの分のスタンプを押してもらう。
完了。 pic.twitter.com/r3QPAFpILF— くりん (@tomorrow8037) 2016年2月11日
健康登山に参加した会員は今後、来山し登山をする度に、手帳に一回、100円で押印することが出来る。
押印するのは高尾山の一施設である薬王院【御護摩受付所】にて。
押印の際は薬王院特製の薬草茶をもてなされるという。
登山の証である押印は、必ずしも登山しなければならないというわけではなく、来山した会員は、その証を受けることが出来る。
つまり、これはケーブルカーなどでも薬王院までやってくればいいということであり、とにかくその場所に来るということが大切であることを暗に示しているのだ。
また、来山時に手帳を忘れてきた会員であっても、日付を手帳に記入しておけば、後日にまとめて押印しても良いということだ。
これはあくまで自己申告であり、ズルをしようと思えば簡単に出来るが、ズルして押印をしても、全く意味がないので、証拠なども必要ないとのこと。
尚、薬王院が指定する健康登山の規定を満行すると、薬王院から精進料理を頂けるという特典もついている。
Twitterユーザーの反応とまとめ
高尾山健康登山。昨年4月から始めて…21回登って…初めての満行達成!!!!まあ、トレーニング?の為スフィアフェス前の1ヶ月で7回も登っているからなww pic.twitter.com/z9fUjq16ts
— 九州人@TOKYO╱遠くへ行きたい16秋 (@asmkon) 2016年5月2日
高尾山健康登山の満業者や100回成満者はこんな感じで名前が掲げられるみたい。 pic.twitter.com/4VOwIgToPg
— 正義 (@togalife) 2016年5月6日
高尾山健康登山 第二回満行の祝い膳。
2年前の夏に始めて、2年間で2回満行できました。 pic.twitter.com/AlyKomSuJ1— 井上雅夫(IPCC報告書研究家) (@co2tw) 2016年8月6日
今日から9月。今朝、窓を開けたらひんやりとした空気が入ってきて気持ちが良かった。まだ暑さは続くようだけど峠は越えたな。
知人が高尾山の「健康登山」を2100回満願成就したというので、お祝いの電話をした。少しあやかりたい気持ちもあって。しかし、凄いことだ。おめでとうございます。— Yoshio Motohashi (@motoyum) 2016年8月31日
高尾山の健康登山にハマったユーザーの気持ちがツイートによく出ている。
手軽に登れる登山スポットとして、長年、我々の知識に深く刻み込まれている高尾山だが、この様な催しも継続させる気持ちを生み出す一つの要因になるだろう。
登山は絶対的に自分との戦いであり、自分との向き合う行為であると、個人的に思っている。
それが健康登山手帳というもので、普段は目に見えない努力の証が可視化するというのは、何とも魅力的であると思うが、どうだろう?